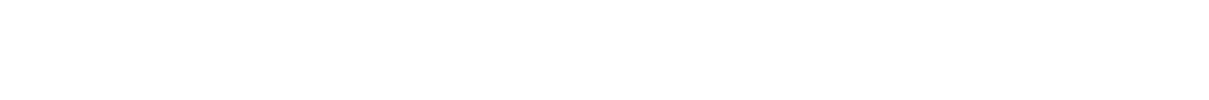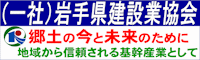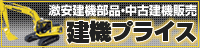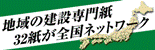コラム集
- ●つむじ風 6月30日
- 6月は、多くの建設企業で安全大会が開かれる時期。弊紙でも多くの企業から声をかけていただいている。安全大会では、墜落・転落、重機、崩壊・倒壊の3大災害と同等か、それ以上に熱中症対策に関することが近年、多く呼び掛けられている印象がある▼一昔前の岩手の6月は、梅雨寒などとも表現されるように、朝方などを中心に、日によっては少し暖房を付けたくなるような日もあったものだが、昨今は夏本番を思わせるような高温多湿の日が多い。熱中症対策は5月から必要な状況となっている▼現場などを見ても、熱中症対策を重視している様子が見受けられる。空調服一つをとっても、ここ数年で一気に普及し、施工現場のみならず、商用店舗などで駐車場の誘導員らもほぼ着用しているくらい見受けられる。作業員の熱中症リスクを判定するAIを搭載したカメラやウォッチ、循環型クーラーを利用したテントなども出てきている▼6月から、職場での熱中症対策が義務化されている。さまざまな対策を講じながら、猛暑を乗り切っていきたい。
- ●つむじ風 6月27日
- 建築家の方と話しているとき、「モダニズム建築」という言葉が出てくることがある。多くは「合理的・機能的だが面白みがない」という文脈で。19世紀末から20世紀初頭は、鉄骨や鉄筋コンクリートなどの新建材というハードと、近代化の中での合理性重視というソフトが合致した時代だったのだろう▼坂牛卓『教養としての建築入門』(中央公論新社、2023年)の中で著者は、オーストリアの建築史家エミール・カウフマンの著書を引用する形で、モダニズム建築は前時代の装飾的な建築にあった外部からの意味付けを排除した、意味を補強されない「自律的な」建築であると定義する。同著を読むと、少し後にはファシズム国家によるプロパガンダ建築やポストモダンなども出てくるが、これ以上突っ込んだ話はぼろが出るのでここまで▼本県における合理的・機能的な直線のモダニズム建築といえば、時代は下がるが県庁舎と盛岡市庁舎か。そういえば両施設とも再整備や新庁舎整備が議論されている。建築物としての意味と在り方にも注目していきたい。
- ●つむじ風 6月26日
- 先日、白杖をお持ちの男性の方と話をする機会があった。その方は、自販機から聞こえる音などを頼りに自分が歩いている場所を把握しているそうで、家まで向かっているとのことだった▼筆者は近所に住んでいることもあり、これまでも何度か、その方と会話をしたことがある。「ここの道が広くなった。歩道にも新しく点字ブロックが整備されて、とても歩きやすくなった」と喜んでいたことが印象深い▼地域に密着し、住民が必要とするインフラの整備に携わることができるのも、地元建設業の仕事のやりがい。大規模なプロジェクトに基づく工事ではなくとも、インフラの整備によって地域にもたらされる事業の効果は数多くある▼住みよい地域づくりのためにも、地域住民や地元建設業が持っている視点、「ちょっとした気付き」などが重要になりそうだ。身の回りにも、インフラの効果を最大化できるような整備の可能性が眠っているのではないか。何気ない日常会話の中にも、将来につながる地域づくりのヒントが隠されているように感じている。
- ●つむじ風 6月25日
- 気象庁は20日、線状降水帯予測精度向上ワーキンググループの第10回会合を開催。観測・予測の強化やメカニズム解明研究の着実な推進、新しい観測機器を導入した集中観測等をより一層推進していくことなどを確認した▼観測体制に関しては、21年度から洋上の水蒸気を捉えるための全球測位システム(GNSS)観測装置を設置した観測を開始。24年度に北陸や東北での線状降水帯発生を踏まえ、25年度は機動的な水蒸気観測を日本海側にも拡充予定だ▼そもそも、線状降水帯にはいまだに分からない部分が多い。そのため、大学や研究機関と連携し、25年度は緊急研究を実施して観測を強化。機構解明を加速させる。観測データや知見を用いた数値予報の精度向上につながるような研究も実施する▼昨年8月に本県内陸で発生した線状降水帯による前例のない降雨のため、道路や橋梁、農地などに被害が生じたことは記憶に新しい。線状降水帯を想定した訓練が行われているが、メカニズムが分かれば対応に確実性や柔軟性が増すだけに、一日も早い機構解明が待たれる。
- ●つむじ風 6月24日
- 厳しい暑さが続く中、各地で開かれる現場パトロールや企業の安全大会では、熱中症への対応が呼び掛けられている。夏季の労働災害ゼロに向け、暑さ対策を徹底していきたい▼今月1日から職場での熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されている。「WBGT値(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業を対象に、症状の重篤化を防ぐため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられた▼対処には、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけることが重要になる。熱中症が疑われる症状例としては、ふらつきや生あくび、失神、大量の発汗が見られるほか、自覚症状としてめまいや筋肉痛、こむら返り、頭痛なども挙げられている▼初期症状を見過ごし、放置して対応が遅れることのないよう、症状の情報共有はもちろん、一人体制ではなくバディを組んでおくことや、応急処置の手順の周知など、万が一に備えていきたい。
- ●つむじ風 6月23日
- 平泉町の国道4号と一関市舞川の主要地方道一関大東線を結ぶ一般県道相川平泉線は、平泉と大東方面を短絡する県道。平泉町など地元では、東北道の平泉スマートICとILC(国際リニアコライダー)の建設予定地となっている一関市大東町を結ぶ最短路線として、見通しの悪い急カーブや狭小区間の改良を求めている▼路線は、平泉町内の国道4号から沿岸部へアクセスする意味合いでも、重要な道路。広域観光ルートとしての位置付けも大きく、沿道には、メディアなどでもたびたび取り上げられる「みちのくあじさい園」が位置する▼観光資源を生かして、県建設業協会一関支部(宇部和彦支部長)では、相川平泉線にアジサイを04年度に植栽した。毎年メンテナンスしており、今年も20日に周囲の草刈りなどを行い、アジサイの順調な生育を願った▼「みちのくあじさい園」は今年度、25日からオープン予定。地元業界の長年の活動が相乗効果となり、多くの観光客らでにぎわうことが願われる。地道な活動が、さまざまな面に波及していくことも望まれる。
- ●つむじ風 6月20日
- 県の建設関連業務では4月から、簡易総合評価落札方式の対象金額を1000万円以上に引き上げるとともに、簡易な業務は設計金額に関わらず価格競争とするなどの見直しを行っている▼従来の建設関連業務は簡易総合評価落札方式のウエートが大きく、企業の技術力を評価する調達方式ではあるものの、受注の偏在を生じさせるという課題もあった。業界団体からは見直しを求める声も多く、今回の変更に至った▼建設産業の最上流部に当たる建設関連業が健全に維持されてこそ、現場での質の高い施工が可能となる。つまり建設関連業務の入札制度を見直すことは、建設生産システム全体の改善にもつながる。この点は県建設業協会も各方面で指摘しているとおりだ▼県建設関連業団体連合会は、同一開札日に同一公所から発注される同種業務における先抜け方式や一括審査方式の導入、チャレンジ型入札制度の創設、企業の地域内拠点の見直しなども要望している。県民福祉の向上と県土の防災力強化の観点からも、必要な見直しは速やかに取り組んでほしい。
- ●つむじ風 6月19日
- 「岩手のインフラ整備は道半ば―」。さまざまな意見交換会や要望会などの場で、よく耳にする言葉だ。建設業界のみならず、市町村の首長からも声が上がることが多い▼広大な県土を誇る本県においては、インフラが社会生活を支えている。内陸部と沿岸部を結ぶ道路は、地域を支えるインフラの最たる例と言える。県土の存続のためにも、確実に機能を発揮する道路などのインフラが必要だ▼東北建設業協会連合会(千葉嘉春会長)の25年度通常総会では、東北地方整備局の西村拓局長が「東北地方の社会資本整備について」と題して基調講演した。西村局長は、国土強靱化などの重要性を語り、高規格道路のミッシングリンクの解消をはじめ、高規格道路と直轄国道のダブルネットワーク機能の強化、津波対策の要となる湾口防波堤の整備などを進めていく考えを示した▼県土を強靱化していくための視点は、日常的な社会資本の整備や維持管理などによって培われていくものではないか。強靱化を今後も推進する上では、地域を熟知している人の目が重要になる。
- ●つむじ風 6月18日
- 最新の建設技術を公開するEE東北25が4、5日の2日間、仙台市内で開かれた。東北建設業協会連合会とVR推進協議会の協力で重機シミュレーター体験会も企画され、実際に体験してきた▼その中で、除雪シミュレーターでは、ソフトで道路構造や標識などを再現したデジタルツイン環境を構築。除雪車両のコックピットを3Dモデルで再現し、リアルな運転環境でステアリングやアクセルなどを操作体験することができた▼体験では、札幌市中心部を左右折をして数百㍍先のゴールを目指すもの。ゴーグルを装着すると積雪状態の街が現れ、ハンドルやレバー、ボタンなどが除雪車両用に再現された。順調だったのは「操作はほとんど普通の車と同じです」というスタッフの話しまでだった▼高齢化や人口減による人材不足の課題解決に向け取り組みが始動している。雪に覆われた道路や道路構造物なども可視化できれば…。実際に体験してみての感想だ。高度な運転技能が求められるが、技能取得機会が少ない除雪車両のオペレーター訓練の大切さも感じる瞬間だった。
- ●つむじ風 6月17日
- 大槌町が整備を進めてきた東日本大震災の追悼施設「鎮魂の森あえーる」。施設は今月末にも完成する見込みとなり、8月5日には記念式典が行われる▼事業は町全体の「追悼・鎮魂」の場として、「被害と教訓」、「復興への想いと感謝」、「希望」を次世代に伝え続けていくことができる施設を整備するもの。建設場所は同町須賀町。町中心部を守る大槌川水門の周辺で、敷地面積約1・45㌶内に芳名碑や献花台、芝生広場などを設置する。施設は23年7月に起工式を実施し、工事が進められてきた▼平野公三町長は記者会見で、記念式典の開催に向け「震災から14年が経つ中、完成に至ることをうれしく思う」と語るとともに、「末永く愛される施設になってほしい」と、町民に親しまれる場となることを願っていた▼8月15日には大槌漁港内の海づくり記念公園で、震災で犠牲になった町民1286人と同数の花火も打ち上げられる。「鎮魂の森」が、東日本大震災から復興への思いを後世へ継承しつつ、訪れる人に命を守る行動を改めて認識させる場になればと思う。
- ●つむじ風 6月16日
- 14日で08年に発生した岩手・宮城内陸地震から17年となった。08年当時の発生時刻8時43分は一関市内で建設業者の環境美化活動に関して取材中だったが、発生したときの状況、翌日には県建設業協会一関支部が被災状況をパトロールする状況や崩落が発生した箇所の土砂撤去作業する様子を、役員に付いて取材したことは今でも忘れない▼同支部では、毎年発生日の辺りに災害情報伝達訓練を実施。今年も、同支部が構築した災害情報共有システム(ASP)やデジタル無線機を活用して、被災箇所や状況を報告したほか、今年度は近年、建設業者で導入が進展している遠隔臨場を活用した被災状況の報告も試した▼同支部では、訓練結果を検証し、さらに体制を充実させていく構え。多発する自然災害に対して、地元建設業者にかかる期待は大きく、体制の充実は頼もしさを感じる▼奇しくも、今年の14日は08年と同じ土曜日。改めて、防災に対する備えの大切さを認識するとともに、防災対策として国土強靱化の推進の必要性を建設専門誌として訴えていきたい。
- ●つむじ風 6月13日
- 今年に入ってから、建設業における労働災害が前年を上回って推移している。事故の型別では、3月、4月と連続して「墜落・転落」と「転倒」が同数。例年だと4月の段階では「墜落・転落」が最も多く、厳冬の年には「転倒」がそれに迫る勢いになるパターンが多いのだが、前年との比較では「転倒」が6人増、「墜落・転落」が1人減▼全産業で見た場合、「転倒」が160人で最も多い。次が「墜落・転落」の66人と、転倒の極端な多さが見て取れる。ちなみに「転倒」「墜落・転落」のどちらも前年比増。岩手労働局では「労災全体の約4割を転倒災害が占め、墜落・転落災害が増加傾向にある」として、全国安全週間の準備期間である6月における対策強化を図る考えを示している▼そういえば6月は「STOP!転倒災害プロジェクト」の重点取り組み期間だったはず。検索すると、転倒災害防止対策のポイントやチェックシートが出てくる。特にもチェックシートは基本的な9項目を押さえており、自社の現状確認と速やかな改善に役立ちそうだ。
- ●つむじ風 6月12日
- 福岡市内の道路が陥没―。さまざまなニュースや、SNS上の話題として取り上げられていた。埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故の記憶がいまだ新しいだけに、日常生活を支えるインフラの重要性に再び注目が集まっていくのではないか▼インフラは基本的な道路のみならず、水道や下水道、電力、通信など多岐にわたる。われわれの安全・快適で豊かな生活を支える共通の財産とも言える▼取材先においては、「インフラは『あって当たり前』ではないのだが…」という言葉をよく耳にする。日々の整備や維持管理、計画的な更新などが行き届かなければ、地域での生活に支障を来してしまう▼11日には、東北建設業協会連合会による25年度通常総会が仙台市で開かれた。総会では国などに対し、公共事業予算の確保などを強く要望することを改めて確認。6県で一致団結し、地域建設業が社会資本を支えていることを関係機関や地域住民らに広く訴え続けたい。国土強靱化実施中期計画に基づく対策が推進されていく中、地域を熟知している建設業界の声は大切になる。
- ●つむじ風 6月11日
- きょう11日は雑節の一つ「入梅」。今年も集中豪雨や台風などにより河川の氾濫や低い土地での浸水、土砂災害などが発生しやすい時期に入った▼国土交通省は、防災に役立つさまざまな情報をより便利に、より簡単に活用できるようにするため「ハザードマップポータルサイト」を運用している。同サイトは、全国を一つの地図上に重ねて表示できる「重ねるハザードマップ」と、市区町村が公開している各種ハザードマップを検索できる「わがまちハザードマップ」で構成されている▼重ねるハザードマップでは、指定した地点周辺の災害リスク情報や避難行動のポイントがまとめて表示される。わがまちハザードマップでは、リンクする市町村作成のハザードマップと併せて利用することで、最新の情報を確認することができる▼災害から命を守るためには、身の回りでどのような災害リスクがあるのか、どう避難すればよいのかなどを事前に確認し、備えることが重要だろう。本格的な梅雨入りを前に、ハザードポータルサイトで災害リスクなどを確認したい。
- ●つむじ風 6月10日
- 宮古市が同市田老地区の旧田老総合事務所跡地に整備し、6日に開館を迎えた市災害資料伝承館。当日は地域住民や子どもたちが施設を訪れ、ガイドの説明を受けながら同市を襲った自然災害の歴史を学んでいた▼伝承館の規模は鉄骨造平屋建ての、床面積422・62平方㍍。施設では、市に被害をもたらしたあらゆる災害の資料と記録を収集し展示。教訓と記憶を風化させることなく次世代に伝えることで、命を守る行動を促していく▼内部には、東日本大震災で被災した道路看板などの実物のほか、津波や水害、大火、防災まちづくりの歴史をパネルで展示。さらに証言インタビュー映像や、ジオラマなど多様な資料をそろえている。高岩将洋館長は「防災を学ぶ新たな拠点として、市民に親しみを持ってもらえる施設にしたい」と語っていた▼周辺には津波遺構「たろう観光ホテル」や、津波被害を受け整備された田老防潮堤などの震災伝承施設も位置している。こうした施設とも連携しながら災禍の歴史を確実に伝え、防災意識の向上を図ってほしいと思う。
- ●つむじ風 6月7日
- 6月からは衣替えの時期だが、近年の気候などを反映してか、軽装となる時期は一昔前ほど明確でなくなってきている。中学校や高校などでも、生徒の体調面を最優先に考え、6月前でも夏服の着用を認めていると聞く▼先週は前半が平年より気温が低く、肌寒さが感じられた一方、後半になるにつれ気温が高くなり平年を上回るなど、寒暖の差を感じた一週間だった。体調管理、特にも身体がまだ暑さに順応していない時期で、熱中症に注意したい▼一関労働基準監督署などが主唱する「夏季死亡災害ゼロ101日運動」が1日から始まっている。①熱中症を防ごう②墜落災害をなくそう③機械設備による労働災害をなくそう④車両系機械による災害をなくそう―を重点事項に掲げ、9月9日までの期間中の死亡災害ゼロを目標に活動が展開される▼四つの重点事項は、前年と同様だが、今年は熱中症への注意が1番目の重点事項に掲げられており、例年以上に重視している姿勢が感じられる。実際に熱中症の発生件数は、ここ数年右肩上がりのように増えているようだ。
- ●つむじ風 6月6日
- 県生コンクリート工業組合によると、25年度の工組員企業の生コンクリート出荷数量は約45万立方㍍。過去最少を更新する見込みで、震災前10年度の6割弱と聞けば、いかに少ない数字か理解してもらえると思う▼私自身はその時を知らないが、ピーク時の生コン出荷は220~230万立方㍍ほどあったそうだ。05年度に初めて100万立方㍍を下回り、10年度の約77万3000立方㍍を底として震災復興需要に伴い需要が回復。15年度は約193万立方㍍とピーク時に近い水準まで持ち直した。19年度以降は5年連続で前年を下回り、24年度は約53万2000立方㍍と6年ぶりに回復したが、25年度は再び減少することが見込まれている▼今後は北上川上流ダム再生事業、岩手県庁舎の再整備、盛岡市の新市庁舎整備、田鎖蟇目道路や箱石達曽部道路、秋田自動車道など、まとまった生コン需要が見込まれる事業は多い。需要期に必要な生コンが供給されずに困るのは、実は発注者の方では。健全な生コン業界の維持を、民間の市場原理だけに委ねてよいのだろうか。
- ●つむじ風 6月5日
- 県土整備部の公式SNS「岩手県県土整備部~美しい県土づくりNEWS」をご覧になっている読者の方も多いだろう。同部のインフラ整備関連の取り組みやイベント情報など、旬な話題を提供している▼このSNSでは、建設業界のPRにも力を入れている。最近の投稿を見ると、バックオフィスDXを導入している企業の事例や、いわて女性活躍認定企業として認定されている地元企業の取り組みなどの情報を発信。SNSを活用しつつ、地域の建設企業にスポットを当てている▼県や建設業界のさまざまな取り組みを知れば知るほど、いかに建設行政・建設業界が、建設業などの魅力の向上のために努力を重ねているのか―ということに気付かされる▼建設行政・業界という大きな視点から、さらに焦点を絞っていくと、受発注者を問わず「県土のために貢献している人」の存在にたどり着くだろう。将来の県土を担う若者たちに、建設分野の仕事の重要性を少しでも知ってほしい。情報媒体が時代に応じて変わるとしても、根幹にある思いは変わらないはずだ。
- ●つむじ風 6月4日
- 建設事業の新材料や新工法、時代のニーズに対応して開発された新技術を公開する「建設技術公開EE東北」。きょう4日から5日までの2日間、仙台市の夢メッセみやぎで開かれる▼建設分野におけるDXを推進するために不可欠なICT技術など「設計・施工」「維持管理・予防保全」「防止・安全」「その他」―の四つの技術分野に952の建設技術が大集結。本県からは10者が出展を予定。会場では、基調講演や各種技術のプレゼンテーションも行われる▼昨年はアシストスーツ体験会を実施。実際に装着しながら、機能や効果を体感することができた。今回は、西館展示場で東北建設業協会連合会とVR推進協議会の協力で、工事現場で行う重機操作をシミュレーターで体験できる企画展示を開催するという▼「広げよう新技術。つなげよう未来へ」をテーマに、今回で34回目の開催となる。現地に来場できない人向けにライブ配信を実施する。時代のニーズに対応して開発された新技術とともに、従来の技術の進化・融合を体感できる場として楽しみにしている。
- ●つむじ風 6月3日
- 大規模林野火災で甚大な被害を受けた大船渡市内では、県が土砂災害対策を図るため応急工事を展開。出水期の到来を見据え、早期完了に向け作業を進めている▼延焼エリアでは、森林の焼損で山の保水力が低下。森林復旧などにより植生の回復が図られるまでの間、土砂災害の発生リスクの増加が懸念されている。県では土砂災害警戒区域などに指定され、焼損が著しく、災害発生の危険度が高い地区29カ所で、応急工事を計画。渓流部に大型土のうや、袋詰め玉石を設置している▼今回の応急工事について県側は、「住家などを守るというものではなく、あくまで土石流の勢いを弱め、住宅地へ達する時間を遅らせることで、避難する時間を稼ぐことが目的」と強調。地域住民に警戒意識、避難意識を高めるよう呼び掛けている▼工事は、災害協定に基づき県建設業協会が推薦した地元企業が担当。県では梅雨入り前の6月上旬を目指し、全て完了させたい考えだ。急ピッチでの作業となるだろうが、労災ゼロを心掛け、無事故無災害で工事を終えてほしい。
- ●つむじ風 6月2日
- 5月は各業界団体の総会とともに、道路や河川整備の整備促進を求める要望活動などを展開する期成同盟会の総会を取材する機会も多い。構成する自治体からの意見も踏まえながら要望内容を精査し、今後、国や県などへ要望に出向く予定がなされている。事業の促進や実現の一助となることが期待される▼同盟会の総会資料などに目を通すと、整備促進を求める事業の中には、昭和初期から始まり、90年以上もの間にわたって進められているものも見受けられた。歴史とともに時間を要する事業が多くあることを改めて感じさせられる▼時間をかけて進めている事業とともに、長年要望し続けているものの、未だ事業化の目途が立っていないような要望項目も見られる。どういった要望の仕方をすれば道筋が見えるか、試行錯誤しながら活動している団体もあるようだ▼近年の雨の降り方や交通情勢など、時代とともに求められるインフラの在り方は変わる。同盟会としても、初期の目的の達成とともに、時代の要請を捉え、効果的な活動を展開していってほしい。
- ●つむじ風 5月30日
- 今年も7月1日から7日まで「全国安全週間」が実施される。実は毎年、安全週間のスローガンに注目している。今年のスローガンは「多様な仲間と 築く安全 未来の職場」。「多様な仲間」が今どきだろうか▼過去のスローガンで使われているワードを振り返ると、2021年の「持続可能な安全管理」はSDGs、11年の「創ろう元気な日本!」は東日本大震災からの復興、02年の「めざすゴールは危険ゼロ」は日本と韓国で開催されたFIFAワールドカップなど。その時代の雰囲気が分かる▼ちなみにスローガン中に「安全」が登場するのは63回。最初は1931年で、一番新しいのは今年。戦時下である44年だって「決戦一路 安全生産」▼ほかに思いつくところでは「職場」の46回、「みんな」の34回、「設備」の16回、「作業」の13回など。ちなみに「設備」は92年以降は登場していない。思いの外少ないのが「安全文化」と「意識」の各4回。「意識」が最初に出てきたのは2013年で、「安全文化」の00年よりずっと後というのは、ちょっと意外。
- ●つむじ風 5月29日
- 「国道281号のトンネルの記事が、新聞に大きく載っていましたね」。取材先において、遠藤譲一久慈市長にお会いした際にかけられた言葉だ。国道281号は、県北の大動脈と表現されるほど、久慈地域にとって重要な路線となる。今後の道路改良に向けて、地域からの期待の大きさが感じられた▼県では、国道281号案内~戸呂町口工区(同市山形町)において、(仮称)下平トンネル(延長569㍍)の本体築造工事を近く公告する。2025年度から3カ年で、トンネル工事を進める計画だ▼同工区の現道は、幅員が狭く線形が不良で、15年8月3日には交通死亡事故が発生。16年台風第10号の際には、久慈川の水位上昇に起因する道路決壊が発生し、広域的な迂回を余儀なくされた。大雨時に道路冠水被害が発生したこともある。今回の改良事業で課題の解消が図られるだろう▼国道281号の整備を着実に進めていき、将来の(仮称)久慈内陸道路の実現に向けて弾みをつけたい。関係者間で道路ネットワークのビジョンを共有することが大切になる。
- ●つむじ風 5月28日
- 流域全体で治水対策に取り組む「流域治水」を促進するため、流域治水の推進に取り組む企業などを「流域治水オフィシャルサポーター」として認定している国土交通省。このほど147の企業・団体等を認定した▼サポーターは、ウェブサイトやSNSなどへの情報掲載やアナウンス、貯留施設の設置、流域の上下流地域の連携を推進する取り組みの実施などを行っている。本県からは㈱東開技術や㈱吉田測量設計が認定されている▼24年度の取り組み実績を見ると、講演や冊子などを通し流域治水対策の重要性を発信したり、治水施設を補完する新たな役割と期待される田んぼダムを広める取り組みなどを展開。流域治水の要となるダムを広く理解してもらおうと、御朱印(ダム印)を作成。管内の直轄管理ダムなど16ダムを対象にダム印を配布するという取り組み事例も見られた▼気象庁によると昨年の梅雨入りは6月23日ごろで、平年は同月15日ごろという。平時の際から流域治水を意識しながら、あらゆる関係者らが連携し流域治水の取り組みを進めていきたい。
- ●つむじ風 5月27日
- 陸前高田市が震災復旧した県指定有形文化財「旧吉田家住宅主屋」は、23日に開館を迎えた。被災から14年。主屋は多くの関係者の熱意により、震災前の姿を取り戻した▼住宅は、江戸時代に仙台藩領気仙郡24村を治めていた大肝入吉田家が、1802(享和2)年に建てたもの。同市気仙町今泉地区のまちのシンボルとして、大切に保存されていたが、震災で全壊。復旧作業には、津波で流出後に回収された部材をできる限り活用したほか、随所に気仙大工左官の伝統的な技法が盛り込まれている▼開館後は、市民や観光客らがさっそく主屋を訪れ、外観や内部を見学。かやぶき屋根を見上げながら、趣あるたたずまいに「すごい」と声を漏らしていたほか、回収した部材がどこに使われていたかよく分からない中での復旧に、感嘆していた様子だった▼今後は市内の視察ルートとして、周囲にある東日本大震災津波伝承館や、市立博物館などと連携した活用も図られるだろう。主屋の価値を発信し、陸前高田の歴史や文化を生かしたまちづくりにつなげてほしいと思う。
- ●つむじ風 5月26日
- 業界団体の総会シーズンを迎えている。総会時に話題として挙がるのは、「仕事がない」や「人がいない」といった内容が多い印象を受ける。事業量に関しては、「震災前の仕事がなかった時期か、それより少ない感触もある」との声まで聞かれる▼担い手をはじめとする人材は、求人を出しても募集がなかなかない面とともに、先行きが見通せないことで、新たな人材の確保をためらっている側面もある気がする。時間外労働の上限規制なども相まって、各企業とも厳しい経営を迫られていることだろう▼建設業に携わる従業員が減っているのは、総会を取材していても感じる。一昔前に比べ会員が大分減ったことに加え、優良表彰を受ける会員企業の従業員も減っている。表彰の対象となる従業員を探すのに苦労する業界団体も多いようだ▼総会に出席する会員が減り、書面表決や委任状の割合が増えた団体もあるという。所用などで出席が叶わない場合もあるだろうが、厳しい環境下にあって、業界が一枚岩となるべく直接顔を合わせられる機会は大切にしたい。
- ●つむじ風 5月23日
- お米をはじめとする食料費の高騰を背景に、高齢者施設や運動部の寮などで、食事を減らしたり、おかわりを禁止したりするなどの対策を講じているところがあるとか。先日、ラジオで聞いた。「高齢者や若者に満足な食事を提供できない国って本当に大丈夫なの?」と文句の一つも言いたくなる▼政府はコメ価格の高止まり対策として、備蓄米の売り渡しに随意契約を活用することを検討しているようだ。早くも「随意契約」という言葉が一人歩きをしているような気もするが、始まってみれば「思っていたのと違う」とならないよう願うばかりだ▼県では東日本大震災からの復旧工事での入札不調を回避するため、随意契約を採用したことがある。ここでは詳しい内容に触れないが、12年秋からスタートしているので、思いの外早い段階から導入していたことが分かる▼大船渡の林野火災に起因する土砂災害への対策も急がれる。有事の際に重要なことは手続き論ではない。市民の安全な暮らしを確保するためには何が必要か。まず考えるべきことはその一点だろう。
- ●つむじ風 5月22日
- 広い県内を往来していると、地域を結ぶ橋梁の多さに気付かされる。地域の大動脈とも言われる道路の橋梁をはじめ、地域生活を支える橋梁などがあり、各橋が持つ機能は多種多様だ▼本紙21日付の3~5面には「橋梁整備事業特集」を掲載。国や県、市町村においては、定期点検の結果などを踏まえ、橋梁の長寿命化などに取り組んでいる▼県土整備部道路環境課は、25年度事業費として121億5152万6000円を充て、橋梁補修・補強工事などを進める。ハード面だけではなく、土木技術者の担い手確保・育成のため、県内の高校生との協働による橋梁点検などの取り組みにも力を入れる。同課によると、久慈翔北高校に関しては、統合・新設に伴う新体制となったことを受け、来年度から開催する方向で検討していくようだ▼教育体制が変化していく中にあっても、担い手の世代が地域のインフラを知る機会を大切にしたい。高校生との協働による橋梁点検やインフラメンテナンス工事現場見学会などが、今年度も夏から秋頃にかけて開催される予定だ。
- ●つむじ風 5月21日
- 男性が積極的に育児を行うことができるよう社会機運の醸成を図ることを目的に2010年度から実施してきた広報事業「イクメンプロジェクト」。男性育休取得率が3割を超えたことなどを受けて、25年度から新プロジェク(PJ)への移行を検討している▼現在、後継事業の名称を募集している。有識者らの意見を踏まえ、事務局案として▽みんオペPJ▽イクシェアPJ▽脱ワンオペ▽共育(トモイク)PJ▽みんなで両立PJ▽その他の名称案―の6案が示されている。キーワードは「共有」だろうか▼厚生労働省はイクメンプロジェクトのHPを開設し、その中で「若者の声 集めてみました」を公開。育休について、若年層男性が84・3%、同女性は91・4%が取得したいという。約7割の若年層が就活で育休を重視しているとも▼先輩イクメン諸氏の後悔や反省、願いを込めて名称案に応募してみてはいかがだろうか。新プロジェクトへの移行をきっかけとして、男性の家事や育児の参画を阻害している職場の働き方の見直しにつながることを期待したい。
- ●つむじ風 5月20日
- 旧矢作小学校の跡地利用を計画している陸前高田市。先週は跡地内に整備を予定する2施設の設計を公告。工事に向けた準備が進められていく▼旧矢作小は、同市矢作町字愛宕下に位置していたが、周辺の小学校との統合により廃校。施設は解体済みとなっている。同小の敷地面積は約1万2000平方㍍。跡地利用については、地元から同小周辺の矢作地区コミュニティセンターと国民健康保険二又診療所、市消防団矢作分団第1部消防屯所の移転整備が要望され、市では3施設の建設を想定している▼このうち同センターと診療所の設計業務については先週、条件付一般競争入札により公告。現在の規模は、センターが鉄筋コンクリート造平屋建ての、床面積401・36平方㍍。診療所は鉄筋コンクリート造平屋建ての246・72平方㍍で、新施設も今のところ同程度の規模を見込んでいる▼事業が進めば、跡地は矢作地区の安全安心な暮らしや、交流を支える拠点になるはず。設計に地元の声を反映させながら、利便性の高い施設を整備してほしいと思う。