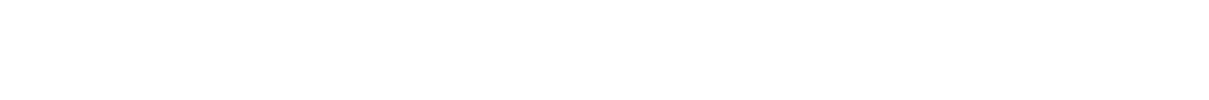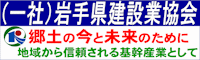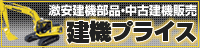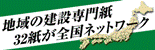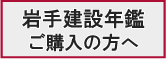コラム集
- ●つむじ風 2月21日
- 合同企業説明会に、出展者として参加してきた。前回と比べて精神的な余裕もあり、合間合間に取材でお世話になった方のブースへあいさつ回りをしていた。パネルにポスターやアピールポイントを飾ったり、モニターでCMを再生したりなど、各社ごとの工夫が光る▼QRコードを活用し、説明資料をはがき大のカードにまとめている会社も。デジタルに慣れ親しんでいる若い世代が扱いやすい形で提示しながら「資料を更新する際に、資料を刷り直す手間を削減できる」と教えていただき、膝を打った▼別日にとある高校へ出向いた際、生徒たちに向けたPRへと話題が移った時には「生徒たちは、内容が同じものでも紙の資料よりデータの資料の方が親しみやすいのではないか」という話も上がった。雑談での何気ない一言だったが、考えさせられるものがある▼発信方法に正解が無いからこそ、次代の担い手層へのアプローチは難しい。彼らによりよく伝わり、理解してもらえる形で仕事をアピールできる方法はないか、今後も模索を続けていきたい。
- ●つむじ風 2月20日
- 岩手労働局が昨年12月に実施した県内建設業一斉監督指導の結果、監督指導を実施した現場のうち61・0%に何らかの労働安全衛生法が認められた。前年度と比較すると9・9ポイントの悪化。岩手労働局では「元方事業者、注文者の関係請負人に対する指導等の徹底」「墜落防止措置の徹底」など労働災害防止に向けた7項目の重点事項の徹底を97団体に要請した▼項目別の違反状況を見ると、「墜落防止措置」と「元方事業者の講ずべき措置等」の違反率が最も高く、ともに66・0%。墜落防止は5・0ポイント改善、元方事業者は25・4ポイント悪化した。具体的な違反内容を見ていくと、墜落防止では手摺りや中さんの設置、元方事業者・注文者では関係請負人に対する指導など、傾向としては24年から大きな変化は見られないようだ▼25年の建設業における労働災害は前年から11・3%の減。死亡者数は記録が残る1950年以来、初めての0人となった。特にも「墜落・転落」災害の減少が大きく寄与した。法令順守の徹底を通じて、納得のいく無事故・無災害を目指していきたい。
- ●つむじ風 2月19日
- 久慈市は、27年4月の開校を目指し、久慈湊小学校の移転改築事業を進めている。施設構造は鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)5階建て、延べ床面積は5111平方㍍。同市では、建設場所が津波浸水想定区域に当たることを踏まえ、新校舎の屋上に津波緊急避難場所を整備する。現段階での総事業費は約44億5000万円と見込まれる市の一大プロジェクトだ▼先日、同市の26年度当初予算案に関する記者会見が開かれた。遠藤譲一市長は移転改築事業に関して、「日本海溝・千島海溝の地震津波も逼迫していると言われる中、子どもたちを守るための大事な事業だ」と強調していた▼15日には、同市市制施行20周年記念式典がアンバーホールで開かれた。会場受付ではパンフレットと合わせて、津波避難場所へのルートマップも配布された。最寄りの避難場所などが地図上に示され、「4階以上へ」「崩落している可能性あり」「標高約20㍍」などの留意点も記載されていた▼新たな校舎で学ぶ子どもたちも防災の思いを引き継ぎ、さらなる市の歩みを進めてほしい。
- ●つむじ風 2月18日
- 警察庁と日本自動車連盟(JAF)は、昨年10月6日から11月7日に実施したシートベルト着用状況全国調査の結果を公表した。全国の一般道で実施した調査結果は、運転席の着用率が99・1%、助手席が96・5%、後部座席は45・8%だった▼都道府県別の結果も公表しており、本県では一般道路で国道4号や同45号、同284号など16カ所で調査。運転席は99・6%、助手席は99・2%。注目すべきは63・1%という後部座席の着用率で、新潟県に次ぐ全国2位。最も低い沖縄県は11・3%…▼高速道路等の着用率も公表している。運転者と助手席はほぼ100%に対し、後部座席の全国平均は79・9%。その中で、本県は94・4%で、全国1位の着用率。最も低い沖縄県の52・0%には驚かされる▼時速60㌔で進んでいる車が壁等に激突した場合、高さ14㍍のビルから落ちるのと同じ衝撃だとか。後部座席のシートベルト非着用時の致死率は、高速道路で着用時の約19・8倍、一般道路で同約3・2倍という。運転者に限らず車に乗ったらシートベルトを徹底したい。
- ●つむじ風 2月17日
- 昨年12月に発生した青森県東方沖を震源とする地震に伴い、気象庁が初めて発表した「北海道・三陸沖後発地震注意情報」。陸前高田市では、同注意情報に関する市民の理解や行動についてアンケート調査を実施し、このほど結果を公表した▼同注意情報は地震発生後、北海道から千葉県の計7道県に発表され、大規模地震への備えが呼び掛けられた。市の調査は先月実施。対象は18歳以上の市民1000人で、506人が回答した▼結果では、注意情報のことを発表前から「知っていた」が39%、「知らなかった」は51%。とるべき備えの内容を「知っていた」と回答した57%のうち、実際にとった備えとしては「すぐに逃げられる態勢の維持」が最も多く、以下「避難場所・経路の確認」「備蓄の確認」「家族との連絡手段の確認」などが続いた。自主避難所の開設についても、82%が「必要」と回答した▼アンケートでは「震災前に、後発地震注意情報が今のように伝わっていれば」との意見も。震災を教訓に注意情報を生かすためにも、周知と備えの徹底が必要だ。
- ●つむじ風 2月16日
- 「インターシップに参加した時、とにかく会社の雰囲気が良かった」。ある企業の新入社員を取材した際、入社の理由を笑顔で答えてくれた。県内での就職を希望していたこともあり、すぐに志望先としてリストアップしたという▼最近は県外への就職を希望する学生・生徒も多いだけに、県内企業でも積極的にインターンシップを受け入れている。企業個々の魅力を知ってもらうことはもちろん、ミスマッチによる早期離職を防ぐことにもなる▼「入社してから10カ月経つが、本当にあっという間。とにかく先輩方に教えられながら、仕事を覚えている最中です」と笑顔で語る姿から、充実した毎日を過ごしているのが分かった。「初めての現場が完成し、そこを車で通る度に、気持ちが高ぶります」とも。建設業の醍醐味を肌で感じたようだ▼そんな新入社員らも、4月からは社会人2年目。今度は先輩として、新入社員を教える立場になる。「教えることは、二度学ぶこと」(フランスの哲学者、ジョセフ・ジュベール)。実力を身に付ける大きなチャンスでもある。
- ●つむじ風 2月13日
- 先ごろ公表された県の26年度の当初予算案。台風10号対応事業を除いた通常分の普通建設事業費は862億5500万円で5・6%増。うち公共事業費は628億7200万円で5・5%増。国の経済対策への対応分を合わせた実行予算は976億4000万円で5・2%増となった▼公共事業費、実行予算ともに、23年度当初から4年連続で増加しており、22年度当初と比較すると公共事業費が134億円余、実行予算が124億円余ほど上回っている。増減率で見ると、公共事業費は約27%増、実行予算は約15%の増。土木が中心の公共事業だけではない。公共事業以外の普通建設事業の通常分は、233億8300万円で6・1%の増▼実行予算はもう少しで1000億円に手が届こうかという勢い。でもなぜだろう、業界内には「事業量が増えている」というムードがあまり感じられない。事業費の割に発注件数が少ないためか、震災復興最盛期の記憶が未だに強く残っているのか。原材料価格や人件費の高止まりというファクターを考慮に入れたとしても、不思議だなぁ…。
- ●つむじ風 2月12日
- 湯田ダムの冬の風物詩「地峡風(ちきょうふう)」の季節がやってきた。先日、西和賀町の現地で山脈の間の「ここだけの風の通り道」と言われる地峡風を体験することができた▼地峡風は、日本海側から吹いてくる西風が奥羽山脈からなる狭いV字谷を通過する時、風速が増大する現象。ビルとビルの間を通過するビル風もその一例という。地図では分かりにくいが、国土地理院の3D地図で高さの倍率を上げて見ると、湯田ダム周辺がV字となっていることが分かる▼先日、取材を兼ねて北上川ダム統合管理事務所湯田ダム管理支所を訪れると、駐車場に着き、降車時点ではそれほどの風を感じなかったが、体験場所に着くと、西からの強烈な風に襲われた。一定方向からの風をイメージしていたが、縦横無尽に吹き付けることもあるとか▼結氷した湯田ダムは水墨画の世界。春夏秋とは異なる姿で迎えてくれる。天候によっては、猛吹雪の体験ができるかも。地峡風の体験は今月27日まで。予約不要で、土日祝日を含む午前9時から午後4時30分までとなっている。
- ●つむじ風 2月10日
- 官民協働により、新たな産業用地の確保を目指す宮古市。市はアクセス道路となる市道の新設を担い、早期の整備を計画している▼市では今回の事業の背景として、昨年のカムチャツカ半島付近や青森県東方沖を震源とした津波警報の発令を受け、複数の市内企業から「安全な場所への移転を検討している」、「市内で移転に適当な用地がないか」といった声が寄せられたことを説明。「機会を逃さないため、できる限り早急な整備を目指す」としている▼用地は宮古短大南側を選定。アクセス道路として計画される(仮称)市道寺ケ沢中谷地線は、津波浸水想定区域を回避する経路にもなり、産業用地からは内陸側で市道の岸ノ前ラントノ沢線、磯鶏金浜線、下大谷地花輪線などを経由し、県道宮古山田線から横断道路の宮古田鎖インターチェンジに入ることができる▼今回のアクセス道路は、避難所への救援ルートの確保など、防災上でも重要な路線となる。産業立地の促進と、安全・安心な地域づくりの両立を図るためにも、円滑な事業の進捗が求められるだろう。
- ●つむじ風 2月9日
- 今回の衆院選は、真冬であることに加え、降雪量の多さなども相まってか、寒さや雪に関する話題が多く取り上げられている。寒さや雪が投票所までのアクセスに大きな障害となって、投票率が下がる懸念などが挙げられ、中には「選挙どころでない」と話す住民の姿も報じられている▼雪は、選挙用ポスター掲示板の設置などに影響を与えている点が報じられているのも、たびたび目にする。ポスター掲示板の設置は、建設業が担うことの多い作業。今回の衆院選では、雪の影響で設置箇所を減らした地域も出ている状況のようだが、県内でも設置に苦労や工夫を要した業者があったのだろうか▼ポスター掲示板の設置では、場所などに関して問題が生じるケースもあるようで、過去にも市町村合併により議員数が増え、ポスター掲示板が大きくなったことで、それまでの箇所に設置できなくなったとの話も聞いた▼費用面も含めて、さまざまな苦労があって選挙運営がなされている。選挙後、こうした労苦が報われるような政治運営となっていくことが切に願われる。
- ●つむじ風 2月6日
- 20年ほど前になるか、県土整備部の幹部職員の一言。「俺たちの仕事の価値ってのは、地域に対する忠誠心なんだよね」。インハウスエンジニアと建設業界が同じ思いを描き、地域のために仕事をしていこうというメッセージだった▼これは今年、県内豪雪地帯の自治体関係者からの感謝の一言。「雪の重みで道路側に倒れた空き家を、除雪を担当している会社が素早くどかしてくれたんですよ。おかげで通行止めにならずに済みました」。対応した企業の人はきっと「仕事だからね。特別なことじゃないよ」と言うのだろう▼ここでもベースにあるのは、地域への忠誠心。建設企業も民間企業である以上、利益を出すのは当たり前だが、損得勘定抜きの忠誠心だって、十分に企業行動の動機付けになる▼冒頭の一言は、岩手・宮城内陸地震や東日本大震災が発生するより前のこと。業界と行政の間に微妙な距離感があった時代でも、地域への忠誠心という目標を同じくしようとする姿勢に、少しだけ救いを感じた。官民が今後も、同じ思いを描けていけるといいのだが。
- ●つむじ風 2月5日
- 県土整備部は、県による初のドローン飛行隊「フェザント・アイ」を結成した。同部は、インフラの点検や災害発生時の被災状況の把握などにおいて、ドローンを活用する▼フェザント・アイは、本県の県鳥であるキジの英語名「pheasant」に、岩手(Iwate)のIと、目のアイに掛けて名付けられたもの。筆者は、このフェザント・アイという名称を初めて聞いた時、「お!格好いいな」と素直に思った。読者の皆さんは、どのような印象を受けただろうか▼フェザント・アイは道路や河川、ダム、砂防堰堤、港湾などの状況確認にドローンを活用する。隊長は県土整備部長が務める。隊員はドローン操縦者51人で構成。各公所につき3人程度が選任されている。先ごろ開かれた結成式では、スタッフジャンパーもお披露目された▼ドローンは、災害発生後のインフラの状況などを、いち早く確認できるのが利点の一つ。岩手を見渡す「目」をもって、広い県土を守る―。フェザント・アイの活動に当たっては、一人ひとりの郷土「愛」が発揮されることだろう。
- ●つむじ風 2月4日
- 気象庁は、季節予報に新しい大気海洋統合モデルを導入し、今月以降に発表する3カ月予報などで利用を始めた。同モデルの導入により1・3カ月予報等の予測精度が向上する▼新モデルでは、大気モデルで雲や積乱雲、陸面などの物理過程が改良され、オゾンが大気に与える影響の精緻化、鉛直層数を100層から128層に増強、アンサンブル予報のばらつきが改良される。海洋モデルでは、計算の高速化や初期値の改良を挙げている▼具体的には、3カ月予報の平均誤差減少や、1カ月予報での季節内変動の予測精度の向上が期待される。実際、昨年8月前半の大雨事例では、従来モデルに比べ新モデルでは、熱帯域の季節内変動とも関係した日本付近の気圧配置の変化をより精度よく予測した実績がある▼1カ月予報の中でも、特に3~4週目の予報精度が向上する。同庁による3~4週目を見ると、「東北日本海側は平年と同様に曇りや雪の日が多い。東北太平洋側では平年と同様に晴れの日が多い」と予報している。将来的には、県別の予報拡大にも期待したい。
- ●つむじ風 2月3日
- 東北地方整備局三陸国道事務所が事業を展開する宮古盛岡横断道路の「田鎖蟇目道路」。現在、終点部に新設する橋梁の下部工など、本線整備に向けた工事や設計の進捗が図られている▼田鎖蟇目道路は、宮古市田鎖から同市蟇目に至る延長7・2㌔。事業区間の国道106号では、16年台風第10号の際、道路決壊に伴う全面通行止めが発生。集落が孤立したほか、代替路がないことから広域的な迂回を強いられたため、事業による災害に強い道路ネットワークの構築が期待されている▼区間内には主要構造物としてトンネル4本と橋梁2橋を整備する計画。2橋のうち、終点部に設ける橋梁は橋長が228㍍で、A1・A2橋台とP1橋脚の工事を推進中。A1橋台は25年度の完成が予定されている。他方の橋梁は橋長43㍍で、このほど詳細設計を入札。着工に向け準備が進められていく▼宮古盛岡横断道路は、救急搬送や広域周遊観光を支える幹線としても地域にとって不可欠な存在となっている。幹線機能の充実に向け、円滑な事業の進展が求められるだろう。
- ●つむじ風 2月2日
- 県盛岡広域振興局土木部では、盛岡工業高校土木科1年生の生徒を対象に、今年度から出前授業を始めた。全5回の授業を通して、県内で働くことへの魅力を伝えていく▼2回目からは、県建設業協会盛岡支部、岩手県測量設計業協会と連携し、現場の生の声を生徒に届けている。生徒たちからは「今までで一番大変だった仕事は」といったものから、事例に上がった施工の具体的な点に関するものまで、実にさまざまな質問が上がっていた。それだけ彼らが働くことを身近に捉えている証左なのだろう▼自分の進路や職業選択を思い返すと、どこで何をしているのかという将来像が全く描けず苦労したが、地元・岩手を離れることは考えていなかった。生まれ育った土地や、その過程で関わってきた人たちへ、仕事を通じて何かを還元したいと漠然と考えていた気がする▼都会で暮らす方が便利な面はあるが、仕事という側面から地元を捉えることで、違った魅力に気付けることがある。見知った場所の新たな面白さを発見する喜びを、生徒たちにもぜひ味わってほしい。
- ●つむじ風 1月30日
- 記録が残っている1950年以来初めてとのこと。速報値ベースであるが、25年の建設業における労働災害による死亡者数は0人。休業4日以上の労働災害の件数は165人で、前年から11・3%の減。今後も年間200人未満の定着が期待されるところだ▼事故の型別で見ると、「墜落・転落」災害の大幅な減少なども影響したか。岩手労働局では「各事業場、業界団体、災害防止団体による安全衛生活動の日々の積み重ねによるもの」と評価し、継続的な取り組みを呼び掛けている▼24年は上半期から死亡労働災害が多発し、県建設業協会と建設業労働災害防止協会県支部が労働災害防止対策の強化に取り組んだ。岩手労働局も局長メッセージを発出するなど、業界の取り組みをバックアップ。これらの取り組みが着実に実を結んでいることがうかがえる▼各方面で新3K、新4Kを掲げて、建設業のイメージアップに取り組んでいる。それにはまず「旧3K」を乗り越えていることが前提。安全に働くことができる職場環境の形成がもっとPRされてもよいのでは。
- ●つむじ風 1月29日
- 東北建設業協会連合会(千葉嘉春会長)、東北公共工事品質確保・安全施工協議会(向井田岳会長)は先週、東北地方整備局に対し、26年度の同局関係予算の確保に係る要望を実施した。「危機管理投資・成長投資」による東北の強い経済の実現とともに、さらなる国土強靱化を図るため、公共事業関係費の大幅な増額の確保などを要望した▼東北各県の建設業協会会長らは、同局に対し、地域建設業が除雪対応や豪雨災害などからの復旧・復興に取り組んでいることを説明。本県建設業協会の向井田会長は「建設業は、地元住民の皆さんから必要とされている存在だ」と訴え、安全・安心な地域づくりなどに向けて、要望内容の実現を求めた▼東北地方は食料などの供給基地として、日本経済において極めて重要な役割を担っている。食料の生産基盤や物流ルートなど、危機管理の骨格となるインフラを下支えしている存在は、間違いなく建設業だ▼東北、岩手が持つポテンシャルの発揮へ―。地域に必要とされるインフラを整備し、国土・県土の力強い成長につなげたい。
- ●つむじ風 1月28日
- 国土交通省は、24年11月に上下水道政策の基本的なあり方検討委員会を設置。2050年の社会経済情勢を見据え、強靱で持続的かつ多様な社会要請に応える上下水道システムに進化するための基本的な方向性について8回の検討会を重ね、このほど第2次とりまとめを公表した▼将来に対する使命を果たすため、「上下水道システムを次世代に守り継ぐ」と強い意思表示をしている。「複数自治体による事業運営の一体化」と「集約型・分散型のベストミックスによる施設の最適配置」を掲げ、上下水道の基盤強化を目指す▼広域連携にはさまざまなレベルがあるが、経営基盤の強化の観点からは、経営主体が単一となり、経営資源(ヒト、モノ、カネ)を一元的に管理するため「複数自治体による事業運営の一体化」を特に推進する必要があるとしている▼事業運営の一体化により、執行体制の強化や運営規模の拡大、一元的なマネジメントなど多様な効果やメリットが期待される。県内には、岩手中部水道企業団という先進事例があるだけに、今後の動向に目が離せない。
- ●つむじ風 1月27日
- 旧商業施設「キャトル宮古」跡地の再整備を計画する宮古市。市は、跡地での施設単体の建設だけではにぎわい効果が波及しにくいなどの現状を分析し、先週、駅前を含めた整備とする方針を示した▼再整備に向けては、官民連携検討業務を委託。年度内での基本計画の策定を目指し、企業ヒアリングなどを実施してきたが、建設資材の高騰などにより事業の成立が困難といった理由から、パートナーとなる民間事業者を見つけられなかった▼こうした状況から市は、周辺との連携の重要性や中心市街地の空き建物の増加など、現状を分析。事業の方向性として、跡地だけでなく事業エリアを広く捉え、駅前を含めたエリアでのハード整備や、近隣の中心市街地とも連携した事業展開とすることを打ち出した▼検討途中の整備イメージ案では、建物は駅側に整備し、老朽化した公共施設の集約化や必要な施設の複合化を図ること、交通空間はキャトル跡地に再編すること、などを示している。案をたたき台として市民の声を聞きながら、再整備事業を進展させてほしい。
- ●つむじ風 1月26日
- 先週から日本列島に「最強寒波」が居座り続け、本県も猛烈な寒さと大雪に見舞われている。考えれば、1年で今が最も寒い時期。ただ大寒も過ぎ、今後は行きつ戻りつしながらも、春の足音が一歩一歩近づいてくる▼連日の降雪のため、除雪が間に合わず、凍結路面をガタガタさせながら車が行き交っている。除雪オペレーターの方々は早朝からの作業が続き、疲れもピークに達していることだろう▼盛岡市では都南村との合併30周年を機に、除雪業務を30年連続で受注した業者に感謝状を贈呈している。今年度受賞した佐々木建設の佐々木吉彦社長は「盛岡市民の日常生活の安全を担っているという責任感と達成感を持って従事している。今後も地域社会とのつながりを大切に作業に努めたい」と語っていた▼雪が降れば夜も寝られず、昼夜逆転の生活を強いられる中、地元への強い思いがあるからこそ続けてこれたのだろう。ただ人口が減っても、除排雪指定路線は年々延伸される。オペレーターが高齢化する中、いつまで今の体制を維持できるのだろうか。
- ●つむじ風 1月23日
- 県は総合評価落札方式の技術提案評価項目を見直し、4月1日以降に入札公告に付する工事から適用する。新規に「県内企業の活用」を評価項目とするほか、土木系以外の工事における災害協定の有無を評価する▼前回の見直しで、工事種別により評価項目を「土木系」と「土木系以外」に分類。土木系以外では「災害活動の実績等」「無償奉仕活動の実績」「維持修繕業務等の実績」を評価項目の対象外としていた▼県と業界との間で、認識の齟齬があったか。特にも災害活動が評価項目から外れたことについては、県との災害協定を締結している団体を中心に、疑問を呈する声が早くから上がっていた▼頻発する豪雨災害に加えて、県内では昨年1月に高病原性鳥インフルエンザ、2月には大規模林野火災が発生。11月に地震に伴う津波注意報、12月には津波警報が発表された。今回の見直しに際して県では「県と業界団体との災害協定の重要性が高まっている」としている。制度はあくまでも手段。課題に対して柔軟に見直す姿勢は、業界側も歓迎だろう。
- ●つむじ風 1月22日
- 県内の橋梁補修工事に携わっている県内建設企業の若手社員と、上司の方々に話を伺う機会があった。若手社員は「実際に働き始めてから、建設業が除雪や道路の舗装補修をしていることを、間近で知ることができました」とほほ笑み、「建設業は社会に欠かせない仕事」という認識がさらに深まったのだそうだ▼上司の方は「世間的には、きついといった建設業の3Kのイメージが強いかもしれません。でも私自身、そう思ったことはありませんよ」と明るく笑い、地域建設業を担う若い世代の活躍に期待を込めていた。若手社員はその言葉を隣で聞き、少し気恥ずかしそうにしつつも、うれしそうな表情を浮かべていた▼建設業は裾野の広い産業。建設現場は年齢などを問わず、皆で共につくり上げるものだろう。無心になって作業に当たる職人もいれば、重機を巧みに動かすオペレーター、会社のさまざまな業務をこなし現場を支える人もいる▼建設業を志す人たちが仕事内容や人間関係に対する不安を少しずつ取り除くような手立て・環境づくりがやはり重要だ。
- ●つむじ風 1月21日
- 「分散より統合、競争より共創」を掲げ、遠野市の遠野東工業団地に整備していたSMC㈱の遠野サプライヤーパークが完成した。コンセプトは「最先端の森」。木と鉄骨のハイブリッド構造で、自然とテクノロジーの融合を目指した環境共生建築となっている▼設計・施工は大成建設。特徴的な屋根は、遠野ならではの山並みに呼応。遠野地場材のアカマツを使用したダブルアーチを採用。約20社のサプライヤーの入居が可能で、研修で国内外から多くの人が訪れることを予想し、施設内には宿泊エリアを設けている▼施設内には「安全道場」を整備。生産現場で起こりうる巻き込まれや転倒、感電などの危険をリアルに再現し、体験を通じて安全の大切さを学べる教育施設となっている。他社の研修受け入れも可能で、安全意識の向上と人材育成を支援していく▼生産現場と建設現場では、作業環境に違いはあるものの、安全の目指すべき方向は同じはず。リスクアセスメントや組織的な安全文化の醸成は欠かせないだろう。学ぶべきは安全への取り組み方だと感じた。
- ●つむじ風 1月20日
- 小・中学部ごとに校舎がある、小中一貫教育校「吉里吉里学園」の施設一体化を計画する大槌町。中学部を小学部の施設に一体化する予定で、今月上旬には条件付一般競争により一体化工事の設計が公告された▼同学園では、児童・生徒数が減少傾向のため、PTA側から各校単独での行事開催が難しくなってきていることなどを理由に、小学部への一体化が要望されていた。校舎の老朽化も進み長寿命化改修が必要な時期を迎えていることから、町は一体化工事と同時に長寿命化の改修工事も実施し、工期・費用の圧縮を図る方針だ▼小学部の校舎棟の規模は、鉄筋コンクリート造4階建ての、延べ床面積2998平方㍍。施設は2004年に完成した。設計業務の履行期限は27年2月までで、建設予定工期には、27年10月から28年12月までを見込んでいる▼一体化整備に向けた設計が発注されれば、工事への準備が本格化していくことになる。施設全体の質の向上を目指し、地域の声も反映させながら、時代に合った魅力的な教育環境を整備してほしいと思う。
- ●つむじ風 1月19日
- わが家の近隣は新興住宅地で、比較的多くの子どもたちが近所に暮らしている。子どもたちが遊ぶ様子は、それだけで活気を感じさせられる▼いま暮らしている子どもたちが成長とともに居住地を変えても、戻ってきて子育てするといった流れになっていくのが理想だろうが、そのために必要な要素の一つとして働き口が挙げられる。地方から若い世代が離れていく要因として、働き口の少なさはたびたび指摘される▼「各地域に点在し、インフラを支える建設業は、雇用を生み出す場として果たす役割が大きい」と話すのは、以前インタビューした首長。その役割を果たすため、各地域に維持し続けていかなければならず、そのために必要なことは言わずもがなだろう▼今シーズンは、こまめに雪かきが必要な日々だが、年齢を重ねるごとに作業の辛さが身に染みる。ただ、自身が年齢を重ねていくと同時に、わが子たちが成長してきたことで、手伝ってくれるようにもなった。近所でも雪かきに励む子どもたちを多く目にし、やはり子どもや若手の存在は頼もしい。
- ●つむじ風 1月16日
- 「意外に格好いいじゃない」。TEC―FORCEの新しいロゴマークを見た印象。TEC―FORCEの増強と多様な主体とのさらなる連携強化の一環として刷新したもの。国土交通省の資料を見ると「盾状構成が『被災地(赤色)を守る』点を強調」「縦線群により、国土交通省に加え、関係する多様な主体が並び立ち、協働で対応する姿を表現」とある▼TEC―FORCEのほか、災害協定を締結した建設企業や団体等の「TEC―FORCEパートナー」、予備隊員、アドバイザーなどが、災害対応の活動時に着用するビブス、災害対策用機械や車両、広報媒体などに使用できるようだ▼大規模災害の発生時、地元建設企業の関係者らが道路啓開など最前線での対応に当たっているが、自衛隊や警察に比べて一般的な認知度が低いことから、PRの重要性が説かれていた。新しいロゴマークが建設業界の認知度向上につながることを期待したい。その半面で「俺たちは注目されたくて災害対応をしているんじゃないよ」という業界関係者の飾り気のなさ。本当に格好いい。
- ●つむじ風 1月15日
- 本紙は、9日付の紙面から「地域に寄り添いながら岩手の社会資本整備へ―県土づくり最前線のリーダーたち」を掲載している。各広域振興局の土木部長・土木センター所長らにインタビューを行い、主要事業や地域のトピックスなどを伺う新企画だ。各地域の明るい話題の一つとなれば大変ありがたい▼インタビューの内容は、ハード事業の進ちょく状況をはじめ、防災・減災対策や担い手の確保・育成などに向けたソフト面の取り組みなど。地域を支える建設業への思いなども伺っている▼取材では、各地域のインフラ整備の効果事例なども取材しており、これまでの県土づくりを踏まえた新たな気付きもあるのではないかと考えている。記事は全14回にわたって掲載する予定だ▼インタビューでは、建設業は「人と未来をつなぐ仕事」、土木工学は「市民のために社会を支える学問」など、さまざまな切り口から建設分野の仕事の魅力を見つめ直すフレーズも多く聞かれた。今年も岩手の未来に向かって、建設行政・業界が一体となり、明るい地域づくりを進めたい。
- ●つむじ風 1月14日
- 「免許はなくてもドライバー。ルールを守って責任ある運転を!」。警察庁ホームページに開設した特設ページ(自転車ポータルサイト)に記されている▼その中で、2026年4月1日から自転車にも青切符が適用されるとしている。16歳以上の自転車運転者が対象。反則金は、携帯電話使用等(保持)は1万2000円、遮断踏切立ち入りが7000円、信号無視(赤色等)や右側通行が6000円、自転車制動装置不良や指定場所一時不停止等は5000円など▼背景には、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車対歩行者の事故の発生件数が増加傾向のため、警察側が自転車による交通違反の指導取り締まりを強化した点を忘れてはならない。自転車乗車中の死亡・重症事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があることも見逃せない▼通勤や通学、遊びなどに幅広い世代が利用する自転車。猛スピードでの歩道走行や通話しながらの運転など目に余る行為も散見される。ポータルサイトなどを参考に、企業や家庭での周知が必要だろう。
- ●つむじ風 1月13日
- 今年の干支は午。「馬」の字の左右を反転させ、福が舞い込むことを祈念する左馬など、縁起物には事欠かない。商売繁盛を願い、店先に置かれることもある左馬だが、個人的には招き猫の愛らしさにも惹かれる▼建設業界で活躍するネコは、今日び一輪車だけではない。イラストレーター・くまみね氏が手掛けるキャラクターの「仕事猫」も大いに活躍している。ヘルメットを被った猫が指差しを行い、「ヨシ!」と安全確認する姿が有名だが、労働災害リスクを見過ごしていることも▼身近に置き換えると肝が冷えつつ、どこか人ごとのような事例も、ユーモラスな仕事猫たちに置き換わることで、親しみを感じるとともに、危険性を客観視できる。中災防の販売サイトでは、彼らの関連用品でコーナーが作られているほか、林野庁や関東地方整備局などの官公庁とのコラボも実現するなど、広く支持されている様子がうかがえる▼岩手労働局主催のいわて年末年始無災害運動実施期間も折り返し。今一度安全への意識を新たにし、安全な労働環境を猫たちと共に招きたい。
- ●つむじ風 1月9日
- 当欄「つむじ風」の執筆は、本紙編集局の記者が持ち回りで担当している。取材先でのちょっといい話や取材で得た気付き、気になったことが主なテーマ。時には業界関係者の隠れた名言や、味わい深い一言も紹介している▼執筆者は30代半ばから50代後半まで。50代記者は本紙読者のボリュームゾーンと重なるか。時には一言多かったり、古い話を蒸し返したりもあるものの、しかつめらしい「社説」ではなく、業界に向けた幅広い話題提供をしていきたい▼実は20代の記者も昨年秋から月1~2回程度、執筆に加わっている。次世代を担う若手社員や、業界を目指す大学生・高校生たちに一番近い世代。百戦錬磨の読者諸氏から見れば、少々青いかもしれないが、建設業やインフラ整備が若者の目にはどのように映っているか、何かのヒントになるかも▼読者の皆さんを飽きさせない話題提供をしていくためには、わたしたち自身の取材に向き合う姿勢が何より重要。末筆になりましたが、本年も「つむじ風」をご愛読いただきますよう、何とぞお願い申し上げます。