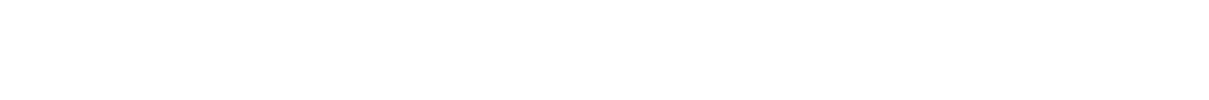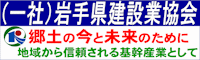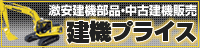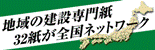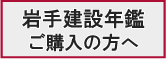コラム集
- ●つむじ風 1月8日
- 本紙では、建設産業の職域代表を務めている見坂茂範参議院議員に新春特別インタビューを実施し、1日付の新年特集号に記事を掲載した。実現を目指している政策の柱や、東北地方のインフラ整備状況の受け止めなど、率直な思いを伺った▼見坂議員はインタビューの冒頭、「『建設産業が元気になれば、日本の産業は元気になる』との強い信念を持ち、仕事に励んでいる」とほほ笑んだ。さらには、仕事の量の確保などに向けた思いとともに、東北における道路ネットワークや河川堤防などの強靱化の必要性を訴えていた▼インタビューで話を伺いながら、広大な岩手を将来にわたって守っていくためにも、建設産業がしっかりと地域に根差していなければならないと改めて強く実感したところだ▼新年に当たって、見坂議員に地域建設業への思いを聞くと、力強くこう語った。「建設業は、永久になくならない産業で、絶対になくしてはならない産業。地域建設業で働いている皆さんには、自信を持って、大きな夢を持って、これからも生き生きと働いていただきたい」
- ●つむじ風 1月7日
- 60歳以上の割合が約4分の1を占める一方、29歳以下は全体の約12%という建設業の技能者。建設業が引き続き「地域の守り手」として役割を果たしていくためには、将来の建設業を支える担い手の確保が急務だ▼国土交通省と厚生労働省は、連携して建設業の人材確保・育成に多角的に取り組んでおり、26年度予算案の概要を取りまとめた。「人材確保」「人材育成」「魅力ある職場づくり」―の3点を掲げ、中でも若者や女性の建設業への入職や定着の促進などに重きを置いている▼継続と拡充が中心だが、新規で建設業の生産性向上の促進と多様な人材の入職拡大に向けた魅力発信に取り組む。ICT導入に係る生産性向上策の深堀調査や、今日的な「技術と経営に優れた企業」を適切に評価するために経営事項審査等の企業評価の見直し検討を実施する▼このほか、建設業へのさらなる入職促進に向け、工業高校生等の就業有望層に対するPR手法の整理にも取り組む。さらに、就業障壁の解消に向けた調査・検討の実施も予定しており、その結果にも注目したい。
- ●つむじ風 1月6日
- 2025年2月に発生した大船渡市の大規模林野火災を受け、1日から運用が始まった林野火災警報・林野火災注意報。県内では沿岸8市町村で一時警報も発令されたが、5日朝、注意報に切り替えられた。火災が多発する時期だけに、引き続き注意していきたい▼今回の警報・注意報は、1―5月に一定の気象条件に達した場合、市町村単位で発令され、対象区域内での火の使用が制限されるもの。「前3日間の合計降水量が1㍉以下かつ前30日間の合計降水量が30㍉以下」などの注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合、警報に引き上げられる▼火の使用制限については、「屋外で火遊びまたはたき火をしないこと」などが示されている。注意報は努力義務だが、警報時、制限に違反すると罰金などが科される場合もある▼大船渡市の大規模林野火災では、平成以降、国内最大規模となる約3370㌶が延焼し、暮らしや産業などに甚大な被害をもたらした。教訓を生かすためにも、警報などで注意を喚起し、火災予防の実効性を高めてほしいと思う。
- ●つむじ風 1月5日
- 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。読者の皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます▼今年の干支は「午(うま)」で、十干と組み合わせた六十干支では「丙午」となる。丙午は「情熱で力強い年」を意味するものだが、それに江戸時代の物語を結び付けた迷信が広がり、60年前の1966年の出生数は前後の年より4分の1少ない約136万人だった▼60年後の2026年には、流石にそのような迷信が影響することはないだろう。ただし、2025年の出生数は約68万人。60年前の半分まで落ち込んでいる。人口減少は先進国共通の課題であり、英国のイングランドとウエールズでは、23年に生まれた男子の名前のトップが「ムハンマド」というから驚きだ▼これからはジェットコースターが最初の山を下りるように、人口減少のスピードはどんどんと加速していく。今後、既存インフラの老朽化が進行し、維持管理費が増大する中にあって、「群マネ」の導入は待ったなしであり、点検などでの技術革新も不可欠だ。
- ●つむじ風 12月26日
- 25年の本紙は、本日付で納刊となります。今年1年ご愛読をいただき、心より感謝を申し上げます。26年も引き続き建設産業界の社会的価値の最大化に向け、有意義な情報発信に努めてまいります▼県営建設工事で総合評価落札方式が初めて試行されたのは06年。技術と経営に優れた企業の受注につながる制度と期待され続けてきたが、近年は受注の偏在など新たな課題が業界を悩ませている▼今年は県営建設工事と建設関連業務において、総合評価落札方式の見直しが行われた。県営建設工事では「チャレンジ型」や、工事種別を「土木系」と「土木系以外」として評価項目を再区分するなどの見直しが行われたが、業界と県当局の間での評価項目の解釈に対するすれ違いなど課題も残した▼あえて誤解を恐れずに言えば、総合評価落札方式に制度疲労が出ていないか。細部の見直しを繰り返しているうちに、本来の趣旨が見えなくなるのはよくある話。だからといって底無しの受注競争は御免被りたい。ここで文字数が尽きた。皆さまよいお年をお迎えください。
- ●つむじ風 12月25日
- 「国土強靱化」という表現が用いられるようになって久しい。テレビ番組などでも、国土強靱化のキーワードを目にすることが多くなったと感じる▼防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策は、2025年度で最終年度。26年度以降は、第1次国土強靱化実施中期計画に基づき、施策が進められる見通しだ。中期計画の柱の一つには、地域防災力の強化が掲げられている▼県建設産業団体連合会(向井田岳会長)と県建設業協会(同会長)は23日に、県に対する建設産業振興対策の要望を実施した。建設関係予算の継続的な確保と国土強靱化をはじめ、県民が暮らしやすい地域づくりなどに向けて、さまざまな視点で要望・提言した▼日本に生きるわれわれの生活は、多くの社会資本によって成り立っている。どれか一つでも欠けてしまうと、日々の暮らしに大きな支障を来すことだろう。建設産業が広い県土にしっかりと根差す―。これもまさに国土強靱化の根幹をなす考え方。26年度以降の強靱化施策の展開においても、地元建設産業の視点を大切にしたい。
- ●つむじ風 12月24日
- 大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、消防庁と林野庁は8月に報告書を取りまとめた。同報告書を受け、気象庁は両庁とともに、記録的な少雨時に火の取り扱いに対する注意喚起を行う新たな取り組みを始めた▼具体的な取り組みの中で、林野火災予防ポータルサイトがある17日に開設され、現在の気象状況や今後の見通し、火災予防の知識などを掲載。火災予防の知識(外部リンク)で、森林研究・整備機構森林保険センターの「山火事に関する研究等」は興味深い内容が並んでいる▼消防庁による林野火災の年間発生件数を見ると、1974年の8351件をピークに以後、減少傾向となり、近年は1300件前後で推移。24年には出火件数が初めて1000件を下回ったが、今年2月に大船渡市、同年3月には岡山市などで大規模な林野火災が相次いで発生した▼大規模な林野火災は、特に2~5月に多く発生する傾向にある。出火原因は、たき火や火入れ、放火(疑い含む)など人に起因するものがほとんどだ。ちょっとした火の取り扱いから注意したい。
- ●つむじ風 12月23日
- 東日本大震災で被災した宮古市田老に整備され、運転を開始した夜間連系太陽光発電所。夜間の電力供給を図るもので、20日には竣工式が開かれ、関係者は脱炭素社会の実現に期待を寄せていた▼同発電所は、昼間に発電した電気を蓄電設備に充電。夜間に送電することで、隣接する既設発電所とともに、昼夜を問わず安定的な電力の供給を図るもの。事業主体は日本国土開発㈱と宮古市が出資する田老発電合同会社で、2024年10月から建設が進められてきた▼同市では震災復興の施策の一つにスマートコミュニティ構想を掲げ、日照時間が長い宮古の利点を生かし、太陽光発電事業を推進。夜間連系太陽光発電所は、脱炭素先行地域づくり事業の一環として整備された。太陽光パネルの総容量は2969キロワットで、一般家庭に換算すると623世帯分の電力を供給できる▼竣工式で中村尚道市長は、「地産電源の拡大において重要な役割を果たすもの」と期待を込めた。地域の再生可能エネルギーを最大限に生かすことで、電力の地産地消を推し進めてほしい。
- ●つむじ風 12月22日
- 合同企業説明会に出展者側として参加してきた。実際に立ち会ってみると、多くの魅力的な企業がある中で、弊社に興味を持ち、ブースを訪れてもらえる出来事の得難さとありがたさを強く実感する▼弊社のみならず、建設業界においても、担い手不足が叫ばれて久しい。対策としてICTの導入やDXの発展が進み、省人化が進んでも、社会が人と人の関わりに根差して発展している以上、最後には人の力が必要になる。しかし、その支え手になる人がいないジレンマ▼安全パトロールの取材に伺った際、自分にも現場の感想を話す機会をいただいたことがある。素人なりの感想にも、熱心に耳を傾けていただいた。拙い感想だったと自省していると「立場が違えば、ものを見る目線も違うものだし、挙げられた意見が安全につながっていく」と激励までいただいた▼集団をより洗練していくためには、物事を見つめる多くの目が重要なのではないだろうか。「目」の多様性を保つためにも、改めて担い手確保を重要な課題として共有し、対策を講じる必要がある。
- ●つむじ風 12月19日
- 11月9日に発生した本県三陸沖を震源とする地震で津波注意報が発表され、久慈港と大船渡港で最大20㌢の津波を観測。今月8日の青森県東方沖地震では津波警報が発表され、久慈港では最大70㌢の津波を観測した。この間、県の水門・陸閘自動閉鎖システムは全て適正に稼動していたそうだ▼このシステムは東日本大震災で水門・陸閘の閉鎖作業を行った消防団員48人が津波の犠牲になった教訓を踏まえ、操作員が現地に向かう必要がない体制をつくるために導入したもの。システムの導入が公表されたのが15年1月、本格運用が始まったのが17年7月31日。なかなか歴史のあるシステムであることが分かる▼当然のことだが「自動」はメンテナンスフリーを意味するものではない。10年近くの間、システムと現地の鋼構造物を維持管理する人材があってこそ、有事の際に防災インフラが適正に稼動する。後発地震注意情報の呼び掛け期間は終了したが、緊張感が解けない状態が続く。「維持」の対象はシステムや構造物だけではない。その担い手が健全であることも重要だ。
- ●つむじ風 12月18日
- 県などの主催による「希望郷いわて流域治水シンポジウム2025」が14日、岩泉町で開かれた。県立岩泉高等学校の生徒らも交えながら、水害に備えたハード・ソフト対策の事例発表やパネルディスカッションなどが行われた▼岩泉高校2年の生徒2人は、地元小学生を対象とした防災教室の取り組み事例を発表。災害が発生する危険性のある場所がないかなどを、小学生と一緒にジオラママップを活用して考えたことを発表した。生徒たちは「小学生にも的確に伝えるために情報を収集した。私たち自身の理解も深まった」「防災に対する意識を高めるためにも、ジオラマ防災教室を続けたい」と語っていた▼パネルディスカッションでは、地域の防災士から、「流域治水の取り組みを『自分事』にするため、柔らかいネーミングを募集するなど、工夫があればおもしろいのでは」との声も上がった▼高校生らもシンポジウムに参加したことで、流域治水の一つの「深化」が図られていると感じた。水害への備えにさまざまな視点を生かし、流域治水の「真価」を発揮したい。
- ●つむじ風 12月17日
- 本格的な除雪作業を前に、県内各地で除雪機械出動式が開かれた。岩手河川国道事務所水沢国道維持出張所管内の除雪安全祈願祭と除雪機械出動式では、出動式後に前沢防災除雪ステーション近くにある前沢北こども園の園児らを招き、除雪学習会を開いた▼園児らに除雪機械を説明後、園児らの号令で除雪機械のエンジンを始動させた。凍結抑止剤散布の様子や散布車に薬剤を投入する様子を間近で見学。キラキラして見える凍結抑止剤散布に興味津々な園児らの様子が印象に残っている▼園児を撮影しようと除雪機械の運転席に近づくと、手作りの作品が目に入った。「おまもり」「おしごとがんばってください」と描かれたお守りだった。以前、園児からもらったお守りを目に付く場所に飾り続けているという。「効果は抜群です」のオペレーターの答えに周囲は笑顔に包まれた▼西高東低の冬型気圧配置となり、県内でも冬将軍の到来を感じる季節となった。慣れた作業に油断せず安全第一で、健康管理にも気を付けながら除雪作業に当たり、来春を笑顔で迎えたい。
- ●つむじ風 12月16日
- 12日に青森県東方沖で起きた地震は、8日の地震の活動域で発生し、本県など太平洋沿岸域に津波注意報が発表された。年末の忙しい時期。スケジュールの変更に悩まされた人も多かったのではないか▼12日の地震はマグニチュード6・9。本県などで最大震度4の揺れを観測した。8日の地震で北海道・三陸沖後発地震注意情報を発表していた気象庁は、「あくまでマグニチュード8クラス以上の大規模地震を対象に注意を呼び掛けるもの。今回の地震は、対象の地震ではない」としている▼12日は宮古市内にいたが、凍てつく寒さに加え、かなりの強風。沿岸部の道に雪は見えなかったが、盛岡から向かう途中の区界峠は凍結路面で車の運転に苦慮した。仮に本格的な徒歩での避難や、緊急輸送などで内陸―沿岸間の交通が増えるようなことになっていれば、厳しい状況だったに違いない▼青森県東方沖での地震では、発生から津波の到達予想時刻までの時間も短く感じる。工事現場からの避難経路や、避難時の寒さ対策も含め、日頃から備えを万全にしておきたい。
- ●つむじ風 12月13日
- 健康診断の結果が戻ってきた。以前から血圧が高く、継続的に治療を受けているのだが、その他の数値もみな少しずつ基準超え。今回そこに、尿酸値が新たに加わった。痛風の怖さを指摘され、少しビビったものの、未だに大好きなホルモンの煮込みを大盛で食べている▼久々に会った人には開口一番、「太ったな」と言われる。典型的なメタボの状態。自覚症状はないが、複数のリスクが相互に影響することで、動脈硬化を急速に進行させ、心筋梗塞や脳卒中など命に直結する病気の発症リスクが高まるという▼ところで日本人の平均寿命は、男性81・05歳、女性87・09歳(2022年時点)。一方で健康寿命は、男性が72・57歳、女性が75・45歳となっている。男性の約9年間、女性の約12年間は日常生活に何らかの制約がかかる「不健康な状態」にある▼「健康で長生き」が理想なのは言うまでもない。厚労省を中心に「スマート・ライフ・プロジェクト」が進められており、労働者の高齢化が進む建設業にとっても重要な取り組みの一つになるのではないか。
- ●つむじ風 12月12日
- 県生コンクリート工業組合によると、工組員企業の25年度生コンクリート出荷予測は約45万立方㍍と過去最少の水準となる見通し。県アスファルト合材協会は25年度の合材製造数量を、前年度をわずかに上回る約53万㌧と予測している。これらの動きから判断すると、砕石や砂利はそれ以上に厳しい状況であることが容易に判断できる▼25年度の補正予算のうち国交省関係の公共事業費は、国費ベースで2・1兆円となる見込み。国の経済対策に対応した県の補正予算も近く発表されるだろう。いずれも第1次国土強靱化実施中期計画の初年度分が大きなウエートを占めることが予測される▼11月9日に本県三陸沖を震源とする地震、今月8日には青森県東方沖地震と、津波を伴う地震が連続して発生した。既存インフラの老朽化対策や防災機能強化への重点投資と併せて、地域建設業が企業体力を適正に維持する施策が不可欠だ。同時に、県内における主要な資材の安定供給体制を維持することも必要。業界全体が疲弊している中、「困ったら県外から」は通用しない。
- ●つむじ風 12月11日
- 気象庁による「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表が、新聞各紙やテレビなど、多くのメディアで取り上げられていた。東日本大震災の教訓を踏まえながら、今回の注意情報の発表を一つの機会と捉えて、改めて身の回りの防災を見つめていきたい▼東日本大震災の後、三陸沿岸地域では、さまざまな建設工事が同時並行的に進められてきた。当時、復旧・復興工事の現場安全パトロールでは、はじめに現場からの避難経路や避難場所などの説明を受けた。海に近い現場が多かったこともあり、参加者で高台の場所などを確認し合ったことを思い出す▼10日に久慈地域で行われた安全パトロールの現場においても、担当者から「安全教育の一環として、津波避難経路などを指導している」との話を伺った。現場で働く人の安全・安心を確保していく上で、震災の大切な教訓が生かされている▼今後も建設現場には、新規入職者や若い世代が入ってくる。建設技術を日々伝えるのと同じように、現場の防災対策などを相互に確認しておくことも大切だと感じている。
- ●つむじ風 12月10日
- 国道4号北上拡幅(延長12・2㌔)のうち、区間南側の北上市と金ケ崎町境から洞泉寺前交差点の延長2・5㌔が6日午前5時に開通した。1982年から4車線化事業に着手し、43年をかけて事業完了となった▼東北地方整備局岩手河川国道事務所は、開通前の2日に現地説明会を開いた。担当者から交通混雑の緩和や冬期交通の円滑化、沿線自治体の産業振興支援―などの整備効果をパネルで紹介。その中で、北上拡幅の変遷として起点部北側の上空画像には驚いた▼1996年と2023年の比較で、緑が多く残る風景が約30年で一転。工業団地や企業、住宅が整備された様子が一目瞭然。それもそのはず。北上市の企業誘致数は、80年の52社に対し、00年に159社、23年には244社に。供用区間が延びるとともに増加している様子がうかがえる▼実際に開通区間を走行すると、安心感と開放感が向上したと感じた。北上拡幅前後では、金ケ崎拡幅や北上花巻道路などで整備が進んでいる。早期に供用を開始し、より質の高い道路空間が生まれることを期待したい。
- ●つむじ風 12月9日
- 4日に取材で盛岡から大船渡に向かったが、今シーズン初めて雪道の運転を体験。遠野・住田の境にある国道107号の荷沢峠は、雪が7、8㌢ほど積もり、圧雪路面を車が列になり時速30㌔で下っていた▼かなり神経を使う運転となったが、大船渡に着くと雪は降っていても、道路には雪が無い状態。峠の雪道の話をすると、大船渡の地元の人に驚かれた。冬季は、内陸部と沿岸部で景色が一変することも多い。特に沿岸から内陸側に向かう際は、慎重な運転が必要だろう▼この時期、各地で行われる工事現場の安全パトロールでは、積雪・凍結による墜落・転落、転倒災害の防止対策とともに、車両のスリップ事故などへの注意が呼び掛けられている。作業者間で声を掛け合い、対策の徹底を図りたい▼「いわて年末年始無災害運動」でも、運転時の注意事項として、急ハンドル・急ブレーキの回避や、十分な車間距離の確保、橋上・トンネルの出入口等での減速などを挙げている。年末年始の慌しさの中でも、移動時間に余裕を持ち安全運転を心掛けていきたい。
- ●つむじ風 12月8日
- 週間天気予報に雪のマークが続き、除雪出動式や除雪功労者表彰の取材が増えると、冬の訪れを実感する。今年も長い長い雪国の冬が始まる▼除雪機械の大きさには出動式の取材のたび新鮮な驚きがあり、実際に雪を跳ね上げる姿を見ると、能率の良さと迫力に圧倒される。冬季においても、安全な道路を維持し続ける関係者の皆さんに対しては、ただただ頭の下がる思いだ▼除雪においても、担い手の確保・技術の継承が重要な課題として位置付けられる。次世代の方に話を聞くと、操縦技術の奥深さとともによく語られるのが、地域住民への思いだ。「除雪を通して地元の役に立ちたい」「皆さんの生活を支えられれば」といった言葉には、先達から受け継がれた「地域の守り手」としての誇りが、確かに息づいている▼除雪により交通環境を整備してもらっていても、冬場の運転には細心の注意が必要だ。スリップを起こして事故になった夢にうなされ、飛び起きるたび、安全運転への思いを新たにする。今年の冬も、夢が正夢にならず、無事に春を迎えられますように……。
- ●つむじ風 12月5日
- 賛否両論あれど、今年の新語・流行語大賞は「働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相」だとか。てっきり「古古古米」か「緊急銃猟/クマ被害」だと思っていた。主催者に何らかの意図があるのか、実は世の中が「働き方改革疲れ」しているのか▼建設業に24年4月から時間外労働の罰則付き上限規制が適用され、公共工事では発注者指定型の週休2日制が定着しつつある。「建設業も他産業と同様に休みが取れる産業に」という理想に着々と近付いているように見える▼一方で、それが建設業の本質を見失わせていないかと懸念する声もある。青天井で働くことが良いことだとは一つも思わないが、現在の働き方改革が本当に現場のためになっているか、立ち止まり見直すことも必要だろう▼さて俺も流行に乗って「今年は年末まで、働いて働いて…」と言ったところ、同僚から「うちらは働かされて働かされて…じゃないの?」とキビしい一言。なるほど、問題はそこか。大切なのは「働かされる」のではなく「働く」こと。そのために何ができるか。
- ●つむじ風 12月4日
- 県土整備部と県農林水産部では、初の合同企画として、パンフレット「スターが育つ!土台はいわての農林水産業と社会基盤!」を作成。本県から多数のスター選手らが羽ばたいていることを受け、「岩手の人づくり」の土台である農林水産業や社会基盤関連の取り組みなどを紹介している▼早速ページをめくると、県庁の若手職員の集合写真が目次と共に掲載されている。県土整備部県土整備企画室では、「若手職員の皆さんも岩手の将来を担う県庁のスター」と話していた。さらには「積極的に職員の姿を見せていくことで、職員の確保にもつながるのでは。『岩手でこんなに面白い取り組みをしているんだ』と思ってもらえれば」と期待も込めていた▼県庁では5日までパネル展を開催。今後、各地区合同庁舎のロビーなどを活用し、同様のパネル展の開催を予定しているようだ▼パンフレットには、「いわての美味しいお米」「いわての住まい」を作る取り組みなどを掲載している。発注者・受注者を問わず、「インフラを担うスター」が広い岩手を支えている。
- ●つむじ風 12月3日
- 県南広域振興局土木部北上土木センターが発行している「国道107号おおいし情報」。第1号は、現地で法面変状を確認した21年5月1日から20日ほど経過した同月20日に発行。これまでの経緯や国の専門家による調査状況などを伝えている▼今月1日に最新号となる15号を発行。11月30日に開催した開通式典の様子を、内記和彦西和賀町長の開通に対する期待の声とともに発信している。これまで発行した各号を開いてみると、発生から開通までの4年7カ月を振り返ることができる▼個人的に印象深いのは全面通行止めとなっていた道路の惨状を目の当たりにしたことや仮橋を歩いたこと、現場見学会での発破音のごう音と爆風、夏・冬版の仮橋カード、暗いトンネル内に照明がついた瞬間の明るさなど。開通式典のトンネル内での太鼓の迫力ある演奏にも驚いた▼15号には、今月8日から開通記念パネル展を開催するとの告知も。大石トンネル開通に至るまでの復旧の道のりを写真や図解で紹介するとともに、「難工事の克服」など見どころも満載という。ぜひ足を運びたい。
- ●つむじ風 12月2日
- 陸前高田市内の東日本大震災津波伝承館は、22日まで企画展示「災害と火―火災から身を守るために備えること―」を、道の駅側の地域情報スペースで開催している▼過去の大規模火災の事例として、1961年5月に発生した三陸フェーン大火や、2011年3月の東日本大震災津波による火災、大船渡市での2月の林野火災を紹介。火災原因では「たばこ」、「たき火」が多いことなど、火災の種類、件数、起きやすい時期・時間帯をデータで見せている▼火災に強い建築・まちづくりのほか、「定期的にコンセント周りを掃除しよう」「家の中のインテリアに耐火素材を選ぼう」など、家庭・個人でできる備えも提示。口に布をあて、身を低くする適切な避難姿勢や、大規模な火災に対応した避難場所の確認なども促す▼空気が乾燥し、火気・暖房を使う機会が増え、火災のリスクが高まる時期。大船渡市で起きた林野火災も記憶に新しい中、大分市佐賀関での大規模火災は対岸の火事ではないだろう。工事現場も含め、防火対策を再度確認しておきたい。
- ●つむじ風 12月1日
- 国道46号盛岡西バイパスが、11月29日に待望の全線4車線供用した。新たに4車線となったのは、北端の県立美術館入口交差点から北口交差点間の延長3・6㌔。北口交差点付近にはイオンモール盛岡などの大型ショッピングセンターが集積。特に混雑が激しかっただけに、喜びもひとしお▼盛南開発と一体的に進められてきた同バイパス整備。供用区間の延伸とともに沿線の都市化が進展し、沿線地域の人口は当初に比べ2・1倍、事業所数は3・5倍に拡大した。良好な住環境が整備された地域として、地価も上昇傾向にある▼それとともに交通量も増加。並行する国道4号からの交通の転換も進み、同バイパスでは慢性的に交通渋滞が発生。特にボトルネックの2車線区間の混雑度は、県内の直轄国道では最大の1・99となっていた▼岩手医大の矢巾町移転などにより、盛岡広域南部の国道4号の渋滞も著しくなっている。盛岡西バイパスと直結する盛岡南道路が整備されれば、南北に並行する大動脈が二つになり、社会・経済の発展に大きな効果をもたらすはずだ。
- ●つむじ風 11月28日
- 父親が建設業で働いていた。建築の現場監督。「父親が関わった建築物を見るのが誇らしかった」と言えば良い話で終われるが、実は子ども心に事故が心配だった。当時はいまと比べものにならないほど労働災害が多かった時期。父がいない日に事故のニュースが出ると「お父さんじゃないよね」。50年以上経ったいまでも、よく覚えている▼12月1日から来年1月31日まで行われる「いわて年末年始無災害運動」。この運動は、繁忙期である年末年始は積雪・凍結に起因する冬季特有災害が多発する時期でもあることから、職場の安全確保の重要性に対する意識を深め、労働災害の発生リスクを的確に把握して対策を講じることを目的に毎年実施されている▼年末年始無災害運動のスローガンの中に「あなたの安全家族の願い」という一文がある。職場の安全は、企業とそこで働く人のためだけではない。それぞれに家族がいて、職場の安全は家族にとっての安心と幸福でもある。年末年始もご安全に。あ、当時お世話になった皆さん。おかげさまで父はいまも元気です。
- ●つむじ風 11月27日
- 本格的な冬が近づく中、ニュースで、今シーズンの気温や雪の量の予想が話題になっていた。この時期になると、県内の建設会社で除雪作業に携わっていた青年に話を聞いたことを思い出す。その青年は「まだ助手の役割をしていて、今は除雪をする道を勉強している段階。先輩オペレーターの除雪技術はすごい」といったことを話していた▼広大な県土を誇る岩手では、道路が県民らの生活や社会経済を支えている。本県の骨格をなす代表的なインフラとも言えるだろう。地元建設業は、年間を通して、地域を結ぶ道路を支えている。冬場には、地元の路線バスなどが通る前に、除雪を実施している。県民の一人として、除雪オペレーターの皆さんには、感謝の思いしかない▼日頃から県土を見守る多くの人の存在があって初めて、インフラが適切に機能を発揮するものだろう。インフラの機能の維持は、県民生活の安全・安心に直結する▼除雪対応などにおいては地元に根差す会社、人の技術力は不可欠。県土を将来に引き継ぐためにも、地域を支える人を大切にしたい。
- ●つむじ風 11月26日
- 県建築士会花巻支部(佐々木繁樹支部長)と花巻市、県南広域振興局土木部花巻土木センター(長沼輝伸所長)が開いている「世代をつなぐ防災・住まいの耐震授業」。08年度から始まり、17年間で延べ37校で実施した▼このほど、花巻市立笹間第一小学校6年生21人を対象に開催。住宅に使用される梁材の持ち上げや大小の住宅模型を使い、筋交いの有無で揺れの違いを体験し、耐震補強の重要性を学んだ。授業の最後には、起震車(防災そばっち号)で全国各地の震災クラスの揺れも体感▼児童らは11~12歳で、東日本大震災の揺れを経験していない世代。起震車で東日本大震災の揺れを疑似体験すると、座っているイスが暴れ、机にしがみつくことしかできない児童らの様子を目の当たりにすると、社内で経験した当時の記憶が蘇ってきた▼児童からは「体験したことを両親に伝えたい」「耐震補強や耐震診断の大切さを学んだ」などの感想が聞かれた。地震はいつ起きてもおかしくない、人的被害のほとんどが建物の倒壊…。この事実は伝えていかなければならない。
- ●つむじ風 11月25日
- 建設業ふれあい事業の取材に伺うと、ありがたいことに、筆者も乗車体験をさせていただけることがある。バックホウを操作した際、見ていた以上に難しかったが、大きな機械を自在に操る事には、他のものに代えがたい喜びや楽しさがある。改めて、業界への敬意と興味が深まった出来事だった▼子どもたちに感想を聞くと、「面白かった」「楽しかった。またやりたい」とにっこり。順番が一巡した後、「もう一回」と手が挙がることも多い。真剣なまなざしや、浮かぶ笑顔を見るたびに、自分と同じことを感じてもらえたのでは、と思う▼地域を守り、日々の暮らしを支える「地域の担い手」を、未来の担い手である子どもたちに知ってもらうことが重要なことだと思っている。体験の記憶が彼らにとって楽しく、実り多く、そして職業選択の一助となることを願ってやまない▼筆者自身、興味が高じて文章を書き続けた結果、本稿執筆に至っている。子どもたちが自分の興味を突き詰めた先で、また会えることを期待しながら、今後も取材活動に励んでいきたい。
- ●つむじ風 11月21日
- 一日中コーヒーを飲んでいる。以前はコーヒー豆を輸入食品の店で買っていたが、驚くほど高くなった。勢いスーパーで安売りの時に買いだめ。味の違いが実はよく分からない。安売りコーヒーが美味いのか、俺が味音痴なのか▼全国建設業協会は先ごろ、25年度補正予算と26年度当初予算での公共事業予算確保を求める緊急要望を行った。その際、当初予算と国土強靱化予算に資材価格などの上昇分を反映することが必要であると主張したようだ▼国土交通省が8月に公表した26年度予算の概算要求。基本方針の中では、国土強靱化の推進に当たり「近年の資材価格や人件費の高騰の影響等を適切に反映し、今後の災害の発生状況や事業の進捗状況、経済情勢等を踏まえ、機動的・弾力的に対応する」との方針を示している▼国土強靱化を含めた社会資本整備は危機管理投資の要。予算の増額にせよ価格転嫁を容易にする制度設計にせよ、コストプッシュ型インフレに対応した施策が重要となる。俺の味音痴は構わないが、国民が社会資本に対する味音痴になっては困る。
- ●つむじ風 11月20日
- 県では、県内各地域の児童・生徒らを対象に、防災学習や出前講座などを実施している。取材時に、子どもたちから何気ない質問が挙がり、意外な視点に驚かされることも多い▼例えば、砂防関連の出前講座では、児童から「砂防堰堤で津波を防ぐことはできるのか」との質問が挙がった。県の担当職員は「砂防堰堤は、山の奥に造っている施設。海の近くには、津波からまちを守るために、防潮堤という施設などを造っている」と答えていた▼砂防堰堤の造り方や、リサイクル材の使用の有無などに興味を示す児童も―。県側も工夫を凝らし、「皆さんが食べているケーキをイメージしてほしい。ケーキを作る時には、枠の中に材料を流し込んでいる。砂防堰堤を造る時にも、土やセメントなどを枠に流し込み、固めることで出来上がる」と伝えていた▼子どもたちの純粋な目は、「インフラとは何か」「なぜインフラが地域に必要なのか」などを真っ直ぐに捉えている。職員と子どもたちのやり取りの一場面。担い手の確保などに結び付くようなヒントはないだろうか。